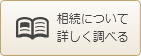遺留分侵害額の請求
遺言書が存在する場合、遺産分割協議は行わず、遺言の内容を優先し遺産を引き継ぐことになります。仮に遺言書の内容が相続人以外の特定の人にすべてを遺贈するというものであっても、方式に沿って遺言書が作成されていれば、遺言書は有効とされその内容に問題はありません。
遺言者の望む形で相続もしくは遺贈が可能となりますが、遺言書が存在することにより本来であれば遺産を相続できた相続人が不利益を被ることになるケースもあります。特に遺言者と一緒に暮らしていた配偶者にとっては今までの生活が脅かされる可能性があります。そのような場合の救済として民法では相続人の一部には被相続人の遺産のうち承継が保証される割合が定められています。この割合のことを「遺留分」と言います。
遺留分について
遺留分はすべての法定相続人に保証されているわけではありません。遺留分があるのは兄弟姉妹(その代襲相続人含む)以外の法定相続人です。遺留分の権利がある人のことを遺留分権利者と言います。
遺留分は法定相続分の1/2と民法で定められています。ただし父母、祖父母などの直系尊属のみが法定相続人になる場合には法定相続分の1/3が遺留分となります。
遺留分侵害額の請求
遺留分権利者は自ら遺留分を侵害している相手(相続人、受遺者、受贈者)に対し、遺留分を請求する意思を示さないと、その分を取得することは出来ません。遺留分権利者がもつ遺留分を請求する権利のことを「遺留分侵害額請求権」と言います。
相続法の改正により2019年7月から「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものが「遺留分侵害額請求権」へと変更になりました。改正前は分割しづらい不動産などすべての遺産が請求の対象でありましたが、改正後は金銭請求のみ可能であると定義がされました。また、「遺留分侵害額請求権」の対象となる生前贈与は相続開始前10年間に行われたものと範囲が定められたのも変更点です。
遺留分侵害額請求権の期限
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内に遺留分権利者は遺留分侵害額の請求を行使しないとその権利は時効によって消滅します。また、相続開始時より10年が経過した場合にも同様です。
遺留分侵害額の請求には遺留分権利者の意思表示を必要としますが、意思表示は侵害している相手先に到達したときに効力が発生するとされています。万が一、相手が通知を受け取らなくても内容証明郵便を利用した意思表示では留置期間が満了した時点で相手先の到達を認めた事例(遺留分減殺額請求の例)もありますので、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行うことをお勧めします。
遺留分侵害額請求後の手続き
遺留分侵害額請求を行っても遺留分を侵害している相手方が話し合いに応じなければ、実質的に遺留分を取り戻すことができません。そのような場合には家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てることにより、家庭裁判所が当事者双方から事情を聴衆し,提出資料を確認して、解決のための助言や解決策を提示してくれます。ただし「遺留分侵害額の請求調停」の申立が遺留分侵害額請求の意思表示になるわけではありません。